人それぞれ、快適に電車に乗る方法は異なりますが
一般知見として記事を書いてみます
この記事にはプロモーションを含むの
基本知識
電車には基本的にモーター車と付随車がある
電車は効率よく走るためや環境への配慮のために(厳密にはケチる為)のために
モーターのある車両、パンタグラフのある車両、なにもない車両等に分かれています
パンタグラフがある車両=モーター車とは限りません、両方を搭載していることがあります
運転台まではここでは考慮しません
また、モーター車にはあのクセのある音のVVVFインバーター(可変電圧・可変周波数インバーター)を搭載していることが今や多いです
路線によっても異なりますが、モーターとパンタグラフ、両方を搭載したり、パンダグラフだけ搭載しているとか
組み合わせが異なったりします
IGBT素子(絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ)を使ったVVVFインバーター搭載車両であれば比較的静かですが
路線ごとに選ぶのは困難です
気動車にはエンジンが搭載されている
気動車のモーターであるエンジンはあまり付随車を使用せず、
動力車であることが多いです
その理由として、電気から走るモーターと比べ、パワーがないためで、
よほど長編成のものでない限り、車両を選べません
電気式気動車にはエンジンと発電機とモーターとバッテリーと付随車がある
まだ採用例がものすごく少ないのですが、仙石東北ラインのほか、JR北海道のH100型やJR九州のYC1系で使用されていることで有名です
1:1の割合でモーター車と付随車があるか、モーター車のみとなります
電車の快適な乗り方 教えます
JRの電車には必ずカタカナを含む型式が書いてあります
その中で以下の文字を含むものはモーター車ですので、選ばなければ良いリストです
| 車両記号 | 意味 | 補足 |
|---|---|---|
| クモハ | 運転台付きモーター車 | モーターの振動やインバータの音が |
| クハ | 運転台付き付随車 | 静か |
| モハ | モーター車 | モーターの振動やインバータの音が |
| サハ | 付随車 | 静か |
| サロ | 付随車・二等車 | 更に静か、一般的にグリーン車等に使用 |
これらのように、共通して含むのは「モ」です
なお、上記のようにカタカナが存在しなければ、電車の型番ごとにWikiPediaを調べるしか方法がありません
地方線区等の短い編成は選ぶのが困難です
気動車ではほとんどありえない
気動車はモーターよりもエンジンの振動のが不快です
しかしエンジンのない車両となると超大編成の気動車を探さなくてはなりません
同じことは有料特急でもあり得る
有料特急の超大編成となれば同じことはありえます
しかし付属編成にはありえないこともありますのでご注意ください
新幹線ではありえないことも
東北新幹線 E5/H5系のモーター車は8割に達しますが、N700S系は東海道・山陽新幹線は87%がモーター車です
また、新幹線の場合、より快適にするための処置がされており気密構造であるため、モーター車と付随車の差はほとんどかわりありません
なお、パンタグラフを搭載している車両であれば主変圧器を搭載しているので、それを避けることによりわずかに快適にすることが可能です
逆に新幹線特有の不快事項はあり、これは容易に防ぐことができず、これを防ぐ酔い止めを試してみるのも良いかもしれません
多くの場合、先頭車両を選ぶと快適
先頭車両がモーター車でないことが多いですので、先頭車両、もしくは最後尾車両を選ぶとよいでしょう
ただし、京急(京浜急行)に乗り入れる電車については、それが通用せず、先頭車両にモーターを搭載していますので、注意しましょう
京急に乗り入れる車両の運用路線は以下の通りです
都営地下鉄浅草線 京成線(AE型有料特急を除く、旧新京成電鉄である松戸線も含む) 北総線 芝山鉄道
京急に乗り入れる車両の先頭車両がモーター車である理由は
高速運転や高加速の為だけではなく、何らかの事故が発生しても車両が重いため脱線転覆に至りにくいのと、信号を確実に動作させるためといわれています
それ以外にも快適にする方法がある
電車・気動車の前後方向の中央に乗れば、必然的にカーブ等での左右の大きな振動を抑えることができます
こちらは新幹線・有料特急などにも有効です
また、座りたいが酸素が足りない方は、振動は多いものの電車の端っこに乗れば、酸素を供給しやすくなります
ドアの前に立っていても酸素は供給しやすくなります
こちらは新幹線・有料特急などは無効です デッキに出入りする人を待つ以外ありません、またはデッキに立つかありません
朝ラッシュ・夕ラッシュの避け方
基本的には根本的に通勤時間を変えないといけません
通勤・退社の時間の最適化
朝にはより早く、夕方にはより遅く出発したほうが快適になりやすいですが、
東京や大阪近辺だとより遅く出発しても快適になりにくいです
フレックスタイムであれば、早めに退社すると良いでしょう
なお、朝早く出発した時は駅構内もしくは駅近隣のカフェで暇つぶししたり
夕方遅く出発するには軽く趣味をこなしたり、外食をするなどすると良いでしょう
飲んでしまうとかえって遅くなりすぎてしまい、更に混雑する可能性があるので注意
住む場所を変えて優等列車に乗る
根本的に住む場所を変えて、東京近辺であれば普通車グリーン車の止まる駅を最寄り駅にする、大阪近辺であれば新快速のAシートの止まる駅を最寄り駅にする、
もしくは有料特急が止まる駅を最寄り駅にするしか方法はないと思われます
始発駅まで向かい、並んで座る
始発駅まで向かって座る方法もあります
朝の場合であれば
あなたの最寄り駅 → 始発駅 → (あなたの最寄り駅) → 会社の最寄り駅
のように行く方法です
ただし、これは何もせず行ったらキセルとなり、旅客営業規則に違反になるだけではなく、犯罪となります
定期券は必ずあなたの最寄り駅 – 会社の最寄り駅の区間で買う必要はありません
あなたの最寄り駅の近くの始発駅 – 会社の最寄り駅 のような区間で
少し増額して購入するようにしましょう
なお、最寄り駅 – 最寄り駅近くの始発駅間の定期代は、会社から支給されないのが一般的です
なお
あなたの最寄り駅 → 始発駅 → 会社の最寄り駅
の場合は追加料金がかかりません
始発駅から座るコツ
現在主流となっているのは20m 4ドア車か20m 3ドア車です
20m 4ドア車では1つの入り口から左右それぞれ7人、合計14人が入れば、席が満員になってしまいます
クロスシート車両の場合は、左右それぞれ8人、合計16人
20m 3ドア車では1つの入り口から左右それぞれ10人、合計20人が入れば、席が満員になってしまいます
並んでる人の人数を数えて、その人数を超えていれば更に次の電車の列に並ぶようにしましょう
先頭車両、最後尾車両を選ぶ
10両編成とか15両編成などの長大編成の場合、先頭車両等を選ぶと若干空いていることがあります
路線によってはこれが全く当てはまらないことがあります、よくリサーチをしておく必要があります
クロスシート車両を選ぶと良いことが
現在東日本地域では減少しているクロスシート車両ですが、
西日本地域では比較的充実しています
20m 4ドア車両と仮定し、同じ長さのドアとドアの間において
ロングシート車両では左右14人しか座れないのに対して
クロスシート車両では左右16人座ることができます
クロスシート車両がある路線では狙ってみるといいかもしれません
まとめ
- JRの場合車両型番に「モ」のつかない車両を選ぶ
- 京急・都営地下鉄浅草線・京成線系列を除けば私鉄などでも先頭車がモーター車ではないので快適
- 電車の前後方向中央に乗れば揺れが少なくなる
- 酸素が欲しければ電車の端に行く
- 先頭車両や最後尾車両を狙う
- クロスシートの車両のがロングシートよりもより多くの人が座れる
- 運賃を余計に払って始発駅から座ってラクに移動しよう
- 根本的な解決をするには住む最寄り駅を変更して優等列車が止まる最寄り駅に引っ越ししよう
なのなの
元取締役、元音楽家、元SE、元レトルトカレー評論家、元ゲーム音楽家(SM調教師瞳シリーズなど)
現在は日本の鉄道事故専任ライターをしているなの
日本標準ネット通販はAmazon
萌え萌えするには日本で唯一取得できるゴンベエドメイン

あたしの中のカワボ ほしいの
パソコン回収のライズマーク ギフト券プレゼントキャンペーン実施中
小さく梱包すれば送料でトクするかも?
Hosted by 773.moe
本記事を引用せずコピペ・同一の意味を掲載した場合には、気軽に訴訟させていただくなの
このブログでは決して右クリック・ソース表示(view-sourceを含む)を行わないでなの 管理者に通知されるの
このブログはインターリンク回線で提供してるの

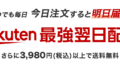

コメント